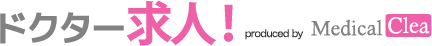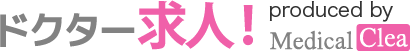在宅医療と救急医療の研究会
消防庁の統計によると、救急車による搬送人数は全国で年間573万6千人ほどに上り、年々、右肩上がりに増えています(平成29年)。その内訳を見ると、じつは高齢者以外では減っていて、増えているのは高齢者の救急搬送です。
また、同じように年々右肩上がりに増えているのが、在宅療養をしている患者さんの数です。毎年10万人ずつくらい増え、現在は650万人ほどに達しています。
救急の現場で起こっているトラブル
そうしたなかで救急の現場で働いている先生方に話を聞くと、在宅医療を受けている患者さんが急変して運ばれてきたときに、救急医として当然のことを行い、命を救うことができたとしても、あとから家族に責められることがある――といった話を耳にすることがあります。
というのは、「終活」という言葉がすっかり一般化したように、「どのように生きたいか」「どのような最期を迎えたいか」を考えている人が増えているなか、「人生の末期段階にさしかかったら、延命治療は望まない」という意思を表明している人もいます。にもかかわらず、本人の意識がなくなり、救急車が呼ばれると、救急隊は心肺蘇生を行って救急病院に連れて行き、懸命な蘇生措置が行われることになります。その後、回復してまた家に戻ることができればいいのですが、そうではなく、一命は取り留めたものの、寝たきりに……ということもしばしばあります。
その途中で、本人の意思を思い出した家族が「やっぱり心肺蘇生はやめてほしい」と伝えても、救急隊や救命医としてはやめるわけにはいかないのです。そうして、望んでいた最期を迎えられなくなってしまい、家族も医療者も辛い思いをする、ということがあると聞きます。
救急医と在宅医の連携
でも、もしも、ずっとその人を診てきて、その人の考えも状態もよくわかっている在宅医の先生が間に入っていたら、違う結末が迎えられたかもしれません。
一刻を争うなかで命を救う「救急医」と、その人に寄り添い、支える医療を行う「在宅医」は、一見、真反対のようにも感じます。ただ、その両者が歩み寄り、連携をしなければ、ますます増える高齢者を支える医療は成り立たない、という考えから、昨年、「日本在宅救急研究会」が発足されました。
そして、11月17日、都内で第2回となる学術集会が行われました。
会の冒頭、あいさつを行った、医療法人社団青燈小豆畑病院長の小豆畑丈夫先生は、この日のテーマであった「本当の良き医療」について話すとともに、「(研究会のなかで)在宅患者さんが急変した時の指針をいずれ作りたい」と展望を示しました。
「医療アクセスへの判断」の早見表
特別講演1で登壇した、日本医科大学教授の横田裕行先生は、「在宅医療を受けている患者が急性増悪し救急で医療を受ける必要がある場合、どのような判断でどの医療機関を受診するべきかという課題に対しては十分な検討がなされていない」と指摘し、医療アクセスへの判断の指針となるマトリックスを考案されました。
縦軸に患者さんとの関係性(いつも一緒にいる/1日1回は会う/2~3日に1回は会う/数日以上会わない)、横軸に患者さんの様子(普段と変わらない/なんとなく元気がない/咳や微熱が出てきた/明らかに普段と違う/意識がおかしい)をとり、それぞれどういう対応が必要かを、パッと一目でわかるようにイラストであらわしたものです。
実際に、小豆畑病院のある茨城県那珂市で試験的に導入し、調査を行っているそうです。
この日は、そのほか、各地域、医療機関で行われている「本当の良き医療」をめざした試みが紹介されました。
住み慣れた地域で最期まで自分らしくいきるということを実現するには、こうした在宅医療と救急医療の連携が各地で求められるのではないでしょうか。
- 会員登録のメリット
- 必要事項が登録されているので求人応募が簡単。
- 優先的に非公開求人や厳選求人をご紹介します。
- 会員のみに開示している情報もweb上で閲覧可能です。