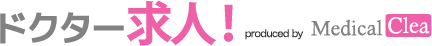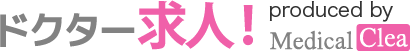AIの進化で10年後の医療はどう変わる?
「ちょっとググってみる(Googleで検索する)」と同じぐらい気軽に、ちょっとChatGPTに聞いてみよう、ちょっとGeminiに聞いてみようと、生成AIを仕事やプライベートに活用する人は増えています。私自身も、すでに手放せなくなりつつあります。
AIのさらなる進化と普及によって、医療と介護はどう変わるのでしょうか。たとえば、10年後の2035年の医療と介護は――。そんな近未来の医療と介護の姿を論じるのが、医師で医療未来学者の奥真也氏の『AIに看取られる日——2035年の「医療と介護」』です。
AIが、医療をより温かくする
AIは、医療をどこまで担うのか。奥氏は「全部」と言います。予防から最期の日まで、すべてのシーンにAIがかかわるようになる、と。
そう聞くと、冷たい未来が待っているような印象を持つ人もいるかもしれません。
でも、奥氏はそんな未来を描いているわけではありません。AIは単なる効率化の道具ではなく、むしろ、「医師と患者さんの関係は、AIを介することで、より対話的で、より人間的なものに成長させうる可能性がある」と結論づけています。この考えに、私はとても共感しました。
いったいどういうことなのか、『AIに看取られる日』の内容をもう少しご説明しましょう。
「名医」が要らなくなる⁉
まず、奥氏は、近未来の医療においてAIは、多くの人が想像するような「医師を手助けする『優秀な助手』」ではなく、「AIこそが診断や治療の中心を担」うようになる、と考えます。そして、「人間の医師はその判断をもとに患者さんとの対話や調整を行う『協力者』になる」と。
というのは、医師の診断精度は経験や知識に左右されるものの、AIは膨大なデータから学習し、常に最新の医学知識を取り入れることが可能です。実際、AIはすでに医療現場で目覚ましい成果を上げていて、たとえば、レントゲンや内視鏡の画像、心電図の波形を解析していち早く病気を発見する、咳の音を聞くだけで病名を見抜くといった技術がすでに実用化されています。
これまでであれば「名医の技」と言われていたようなことを、AIが代行できてしまうのです。そのため、奥氏は「すべての患者さんが『名医』の診断を受けられる時代が来る」と語ります。
AIが誤診したら?
AI診療は、膨大なデータの裏付けによって、誤診や病気の見逃しを限りなくゼロに近づけます。でも、それでも100%の絶対はあり得ません。
では、AIが誤診したときの責任はいったい誰が担うのでしょうか?
奥氏は、自動運転で事故が起きた場合の責任所在をめぐる議論が大いに参考になる、と言います。自動運転にはレベル1から5まであり、自動運転の解禁とともに道路交通法が改正され、レベル3(一定の条件のもとではシステムが運転の主体となり、緊急時にはドライバーが操作を引き継ぐ)の自動運転で発生した事故はドライバーが責任を負うものの、レベル4の自動運転中に発生した事故については利用者(乗客)には責任はないものとされました。
この考えをAI診療にも応用し、「システムを利用する医師ではなく、システムを開発したソフトウェア会社が責任を負い、ソフトウェア会社は万一の場合に備えて保険に加入し、事故が起きた場合は保険会社から賠償金が支払われるべき」と、奥氏は述べます。
AI医療時代、人間の医師の役割は?
患者さんの症状を問診や検査などを通じて調べ、病気を特定するということは、AIに、「人間の医師は太刀打ちできなくな」る、と奥氏は言います。
では、AIがとって代わることのできない、人間の医師の「聖域」とは――。奥氏は、人間医師ならではの役割として、次のようなことを挙げます。
・症例が非常に希少で、ガイドラインがまだ整備されていない病気に対する治療戦略の立案、ガイドラインが当てはまらない例外的なケースへの対応
・患者さんが置かれている状況を深く理解したうえで、心理面のケアとサポートを行うこと(=寄り添いの仕事)
・病気ではないのに病気ではないかと思い込み、不安に駆られてやってくる人に、安心を提供する
・個々の患者さんの社会的な立場や家庭の事情なども考慮した診療を行う
つまり、AI時代の医療では、ガイドラインどおりの診療はAIがやってくれるので、AIを使いこなしたうえで、AIにはできない患者さんの心に寄り添う仕事ができる人だけが医師として一段上のステージにたどり着け、名医と呼ばれるのではないか、と言います。
また、AIがもっと普及すれば、患者さん自身も自分の病気や治療のことをAIに相談するのが、ふつうになるのではないでしょうか。奥氏も、「AIから得られる豊富な情報をもとに、より主体的に自分の治療に参加できるようになる」だろう、と書いています。そうすると、ますます、双方向のコミュニケーションが大事になってくるはずです。
- 会員登録のメリット
- 必要事項が登録されているので求人応募が簡単。
- 優先的に非公開求人や厳選求人をご紹介します。
- 会員のみに開示している情報もweb上で閲覧可能です。